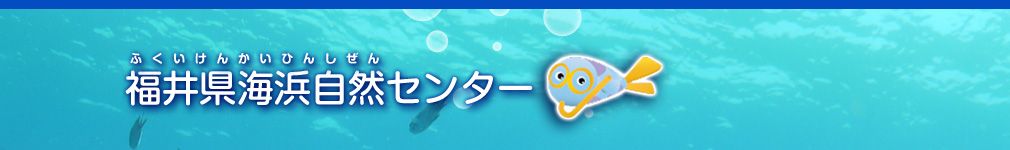三方五湖自然教室「はす川の魚を観察しよう」を開催しました。
2018年7月1日(日)、三方湖に流れ込む最大級に河川であるはす川で、三方五湖自然教室「はす川の魚を観察しよう!」を開催いたしました。
地元で活動するハスプロジェクト推進協議会の方々や龍谷大学非常勤講師の上西実先生を講師に迎え、県環境政策課が実施するせせらぎ定点調査(水質調査)との合同開催となりました。海浜自然センターとしては、久しぶりのはす川観察会!どんな生きものたちに会えるのか、とっても楽しみにしていました。
水質調査では、COD(化学的酸素要求量。水質の指標の1つで、有機物が多く、水質が悪くなるほどCODが高くなる傾向がある。)が例年より少し高い場所も見られたものの、透視度は高く、講師の先生方にサポートいただき、興味深そうに透視度を覗き込む様子がみられました。生きもの観察では、魚が捕れるまで、何度も挑戦する様子や、お孫さんに魚の捕り方を教える姿が伺えました。
最後に、講師の先生方に捕まえた生きものについて教えていただき、私達のごく身近な川にも、たくさんの生きものたちが暮らしていることをみんなで確認することができました。
- 講座開始
- まずは水質調査から
- 透視度を測ってみよう
- 魚捕りの様子
- どんな魚が捕れたかな?
- 他にはどんな生きものがみられたかな?
海のふれあい教室「早めに自由工作スタート!海藻おしばを使ってステキなカードを作ろう!」を開催しました。
2018年6月10日(日)、海浜自然センターで海のふれあい教室「早めに自由工作スタート!海藻おしばを使ってステキなカードを作ろう!」を開催いたしました。
今年度は6月3日に「海藻の体のしくみを知っておいしく食べよう!」、10日午前中に「早めに自由研究スタート!海藻採集と標本作り」と海藻に関する講座をいくつも行いました。この講座も午前中から続けて参加されている方が何名もおられました。
今回は午前中の講座で採集した海藻や事前に採集しておいた海藻を使用し、様々な大きさのケント紙4枚に張り付けました。海藻の色や形を生かし、参加者のみなさんは工夫しながらすばらしい作品を作っていました。夏休みの工作や記念品にぴったりですね。
- 海藻について解説しました。
- 海藻おしばの作り方を説明しています。
- すばらしい作品ができました!
海のふれあい教室「早めに自由研究スタート!海藻採集と標本作り」を開催しました。
2018年6月10日(日)、海浜自然センターと食見海岸で海のふれあい教室「早めに自由研究スタート!海藻採集と標本作り」を開催いたしました。
毎年大人気の講座で、今年度も多くの方にご参加いただきました。東京海洋大学海洋環境科学部の神谷充伸先生にお越しいただき、海藻の種類や陸上の植物と海藻の違い、生えている場所、標本の作り方など海藻について詳しい解説をいただきました。次に海岸へ移動し、海藻を採集しました。この時期は様々な海藻が生えていて、緑藻3種類、褐藻12種類、紅藻13種類を採集できました。センターへ戻って着替えを済ませた後、標本作りを行いました。神谷先生に海藻の名前を教えていただき、海藻を紙の上で広げて、吸水紙や新聞紙を使って標本にしていきました。もちろんこれで完成ではないため、今後紙を交換して時間をかけて乾燥させる作業が待っていますが、きっと夏休みの自由研究にぴったりの作品ができるものでしょう。
この日の午後は「早めに自由工作スタート!海藻おしばを使ってステキなカードを作ろう!」の講座も開催しました。
- 海藻について解説してもらいました。
- 標本の作り方を教わっています。
- 海岸で海藻を採集しています。
- 初夏の海岸は様々な種類の海藻が生えていました。
- 採集した海藻の名前を調べています。
- 採集した海藻を標本にしています。
海のふれあい教室「初夏の磯で生きものを探してみよう!(2回目)」を開催しました。
2018年6月17日(日)、当センター近くの食見海岸で、海のふれあい教室「初夏の磯で生きものを探してみよう!」を開催いたしました(1回目は5月27日)。
最初に磯の生きものや観察の注意点を説明した後、準備をして磯へ移動し、観察開始。この日は潮が引いていて海面が低く、晴天で波も弱いという磯観察には絶好の状態でした。プラケースを使って海中をのぞくと貝や魚が見え、タモ網で捕まえました。イトマキヒトデやイソガニ、ホンヤドカリ、キヌカジカ、メジナなど様々な種類の生きものを採集できました。その後センターへ戻り、生きものの名前を調べてセンター職員が生きもの解説を行いました。最後に全員が採集した生きものを集め、細かな違いを確認し、海の多様性について学びました。参加者からは「子どもがすごく楽しそうで親も夢中になって生きものを採集できた」「子どもたちが海の生きものに触れる機会ができて、また参加したい」等の感想がありました。
- 観察のポイントや注意点を説明しています。
- 準備をして磯へ出かけます。
- 磯観察開始!
- 岩の間にいる生きものを捕まえています。
- ブロックの穴は生きものを捕まえる絶好のポイント!
- 子どもも親も夢中になりました。
- 図鑑やクリアファイルで生きものを調べています。
- 生きものの解説をしています。
- 生きものを集めるとミニ水族館になりました。
スノーケリング自然教室「みんなで環境美化!海域公園クリーンアップ」を開催しました。
2018年6月16日(土)、スノーケリング自然教室「みんなで環境美化!海域公園クリーンアップ」を開催いたしました。
2018年度のスノーケリング教室も、このクリーンアップからいよいよ幕開けです。午前中は食見海岸、午後は船で烏辺島に渡り、清掃をする予定でしたが、波が少し高かったため、食見海岸のみの清掃となりました。
海中を清掃するグループと、海岸の清掃をするグループに分かれて活動を開始しました。海中はゴミが少なかったものの、海岸には国内外を問わず、ビニール袋やペットボトルなどの家庭から出たであろうと思われるプラスチックゴミや、漁網や浮きなどの水産業関連のゴミ、苗ポットなどの農業関連のゴミが多くみられました。
参加者のみなさんの頑張りのおかげで、食見海岸はとてもきれいになり、地元の区長さんからは、お礼の言葉をいただきました。これで夏を迎える準備も万端!といった具合ですが、その反面、近頃、問題視されている海で起こっているプラスチックゴミ問題が、本当に深刻であることがよく分かりました。海浜自然センターでは、海の楽しさを伝えるのと同時に、ゴミの問題のこともしっかりお伝えしていきたいなと改めて感じました。
クリーンアップに参加していただいたみなさま、どうもありがとうございました。
- 海中清掃の様子
- 海中からゴミを引き上げます
- 海岸清掃の様子
- きれいな海を未来に残そう!
海のふれあい教室「初夏の砂浜で生きものを探してみよう」を開催しました。
2018年6月9日(土)、小浜市西津浜で、海のふれあい教室「初夏の砂浜で生きものを探してみよう!」を開催いたしました。
まず、福井県立大学海洋生物資源学部の富永修先生から、講座を行うことの意義や環境について知ることの重要性を教えていただきました。
次に浜へ移動し、水深を変えて海水の塩分濃度の測定を行い、濃度差から水深によって棲む魚の種類が違うことを学びました。
そして生きもの採集です。みんなで小型の地引網を引っ張り、網の中をタライに出してみると・・・魚やエビが何種類も出てきてビックリ!さらに手網で生きものを捕まえた人もいました。
最後に何が採集できたか調べ、富永先生に解説をしていただきました。生きものだけでなく、生態や研究、若狭のおいしい魚の話まで大人も子どもも楽しめる話に夢中になりました。
参加者からは「短い時間でも多数の生きものが採集できて驚いた」「環境を守る大切さがよく分かった」といった感想をいただきました。
- 海水の測定について解説しています。
- 手網で生きものを採集しています。
- みんなで地引網を引っ張っています。
- 地引網から出てきた様々な生きものに大喜び!
- 図鑑を使って生きものを調べています。
- 採集できた生きものの解説を行いました。
<観察できた生きもの>
ヒイラギ、ヒモハゼ、ヒメハゼ、ダイナンギンポ、ボラ(幼魚)、イシガレイ、マハゼ(幼魚)、エビジャコ、テッポウエビ、イソスジエビ、クルマエビの仲間(稚エビ)
- イシガレイ
- ヒイラギ
- ボラ(幼魚)
- マハゼ(幼魚)
- ヒモハゼ
- クルマエビの仲間(稚エビ)
- テッポウエビ
西津浜での生きもの観察ですが、3ヶ月に一度、市民参加型の調査が行われています。どなたでも参加できます。次回の日程が決定次第お知らせしますので、今回参加できなかった方も、また参加したい方もぜひご参加ください。
海のふれあい教室「海藻の体のつくりを知って、おいしく食べよう」を開催しました。
2018年6月3日(日)、海のふれあい教室「海藻の体のしくみを知って、おいしく食べよう」を開催いたしました。
海浜自然センターでは、イカと魚では同じような講座を開催していますが、実は、海藻ではこれが初めて!みなさん参加してくれるかな・・・すごくドキドキしました。(でも、どうしてもやりたかったんです!)
さて、当日は、23人とたくさんの方にご参加いただきました。大島漁業協同組合女性部長の子末とし子さんを講師に迎え、採取したテングサの処理方法についてお話を伺ったり、ところてんを押し出す体験などをさせていただきました。
さあ、いよいよテングサを使った海藻ゼリー作り!子末さんにアドバイスいただきながら、テングサを煮出したり、濾したりしましたが、鍋がすぐに吹きこぼれるため、目が離せず、大忙しとなりました。濾した液に、ジャムやジュースを加え、思い思いの味に仕上げました。
ゼリーが固まるまでの間、海藻の種類や不思議な体の作り、海の中での役割、人間の利用等について、お話をさせていただきました。
さて、そろそろゼリーは固まったかな?どのゼリーもとっても美味しそうに出来上がりました。参加者の方々からは、「海藻ゼリーは作るのも楽しかったし、美味しかった。」、「海藻に興味を持ちました。」、「もっと海藻の話が聞きたい。」といった感想をいただきました。
海浜自然センターでは、これからも、海の生態系や生産力を下支えする「海藻」についての講座を、いろいろな角度から開催していきたいと考えています。楽しみにしていただけるとうれしいです。
- 講師の子末とし子さん
- ところてんを押し出してみよう
- テングサを煮詰めます
- 海藻ゼリーの味付け
- 少しだけ海藻についてお勉強
- 美味しそうな海藻ゼリーの出来上がり
海のふれあい教室「初夏の磯で生きものを探してみよう!(1回目)」を開催しました。
2018年5月27日(日)、当センター近くの食見海岸で、海のふれあい教室「初夏の磯で生きものを探してみよう!」を開催いたしました。
最初に磯の生きものや観察の注意点を説明した後、磯へ移動し、観察スタート!この日は晴天で波もほとんどないという磯観察には絶好の状態でした。プラケースを使って海中をのぞくと貝や魚が見え、タモ網で捕まえました。イソガニやイシダタミ、ドロメ等様々な生きものが採集でき、中にはイトマキヒトデやムラサキウニ、アメフラシを捕まえた方もいらっしゃいました。その後センターへ戻り、生きものの名前を調べてセンター職員の生きもの解説を行い、最後に捕まえた生きものを海へ戻しました。参加者からは「子どもが自分でカニを見つけて捕まえることができてとても喜んでいた」「先日開催された砂浜の生きもの観察とは違った生きものが見れて楽しかった」等の感想がありました。
- 観察の注意点等を説明しました。
- 天候もよく、波もない観察日和です。
- 生きものを採集しています。
- 親子で探し中。
- 生きものの名前を調べています。
- アメフラシの解説を行っています。
三方五湖自然教室「外来種バスター①カエルやカメの捕獲と解剖!」を開催しました。
2018年5月26日(日)、三方青年の家を会場に、三方五湖自然教室「外来種バスター①カエルやカメの捕獲と解剖!」を開催いたしました。
始めに、里山里海湖研究所の高橋繁応先生に、湖岸で撮影されたミシシッピーアカミミガメ(以下アカミミガメ)の写真を見せていただきました。次に、愛知学泉大学の矢部隆先生に、アカミミガメやウシガエルが増えると、地域の自然がどのように変わってしまう恐れがあるのかを教えていただきました。
そして、みなさんお待ちかね。外来種を捕獲するためのかご網を引き上げました。例年、外来種だけではなく、在来の生きものも見られます。今年は、どんな生きものが見られるかな?あちこちで、大きなウシガエルの大人やオタマジャクシに驚きの声が上がりました。大きなナマズも捕れました!アカミミガメの赤ちゃんが捕れた時には、こんなにかわいいのに駆除しないといけないなんて…と少し悲しい気持ちになりました。
ウシガエルの解剖では、ザリガニやカエルなどなんでも食べている様子や、たくさんの卵を持っている様子が観察されました。
最後に、矢部先生が「人の手によって持ち込まれた外来種は、本当は悪者ではなく、被害者です。二度と同じ過ちを繰り返さないよう、駆除される外来種も在来種と同じ命なんだということを決して忘れてはいけません。」とお話されていたのが、とても印象に残りました。まずは、私達に出来ること、「逃さない・放さない」が第一歩ですね。
- 高橋先生のお話
- さあ!いよいよ出発です
- かご網の引き上げ作業
- どんな生きものが見られたかな?
- ウシガエルの解剖
三方五湖自然「バードウォッチング 初夏 超早起きは10文の得!」を開催しました。
2018年5月19日(土)、小浜市上根来にて、三方五湖自然「バードウォッチング 初夏 超早起きは10文の得!」を開催いたしました。
今年度2回目のバードウォッチング。開催前夜から風雨が強く、雨具をつけての観察となりました。集落手前の杉林では木々の揺れる音や雨具に雨の当たる音も大きかったのですが、トラツグミやサンコウチョウ、アカショウビンなど様々な夏鳥の鳴き声が聞こえました。さらに集落を過ぎた畜産団地付近ではホオジロやキセキレイ、アオバトなどの野鳥の姿を見ることができました。風雨が強く霧が深いことから予定していた遠敷峠までは行けませんでしたが、嶺南地区で観察できる主な夏鳥の鳴き声を中心に観察することができました。
- 杉林で野鳥の大合唱を聞いています。
- 畜産団地で数種類の野鳥の姿が見られました。
- 観察終了後に鳥合わせを行いました。
次回のバードウォッチングは12月1日(土)9:00~11:30、三方湖周辺でカモ類を観察する講座を行います。お楽しみに!